
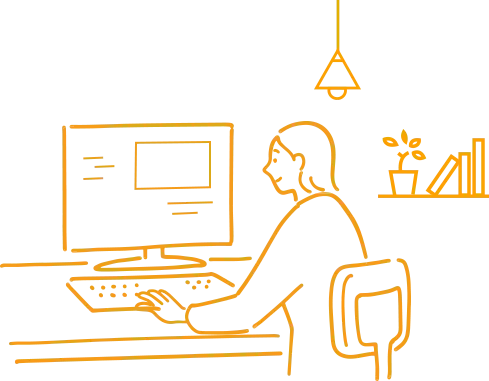

身近な事例から学ぶ、争続を防ぐための3つのポイント
こんにちは。神奈川県横浜市みなとみらいの税理士の古閑です。
今回は、「相続で揉める家」と「揉めない家」は何が違うのか?について、実際によくある事例を交えて、事前にできる対策をお話ししたいと思います。
今回は、専門的なワードは出来る限り使わずに説明していきたいと思います!

あるお客様、Aさんは80代のお母様を亡くされたあと、相続をきっかけに弟さんと絶縁状態になってしまいました。
原因は「実家の不動産」を誰が相続するかをめぐる対立です。お母様は遺言書を作っておらず、相続人はAさんと弟さんの2人。
実家は評価額こそそれほど高くはないものの、Aさんが同居しており、住み続けることを希望していました。
しかし、弟さんは「不動産は分けにくいから、売却して現金で分けよう」と主張。感情がぶつかり合い、調停まで発展しました。
結果として、実家は売却され、Aさんは新しい住居に引っ越すことになり、いまだに兄弟の関係は修復できていません。
Aさんのケースに限らず、相続で揉める家庭には共通点があります。
不動産は分割しにくく、共有名義になると後々トラブルになりがちです。「家は兄が、現金は妹が」といった分け方ができない場合、感情のもつれも生じやすくなります。
遺言書がない場合、相続人全員の同意が必要になり、意見が食い違うと協議が進まなくなります。
「親は公平に分けるつもりだったはず」といった“想像”が、争いの火種になることも多くみられます。
生前に相続について話し合ってこなかった家庭では、いざ相続が発生したときに価値観の違いが表面化します。
「兄ばかり優遇されていた」など、過去のわだかまりが一気に吹き出すこともありますので、希望的観測で考えていると大変になりがちです。
一方で、揉めなかった家には明確な共通点があります。
「どこに何があるか分からない」「預金通帳が見つからない」といった状況では、調べるだけで時間がかかり、誤解も生じます。
元気なうちから「財産目録」を作成しておくと、家族が安心して対応できます。
法的に有効な遺言書、特に「公正証書遺言」は、家庭裁判所の検認が不要で、トラブルを防ぐ強力な手段です。
「家は長男に、現金は次男に」と具体的に書いてあれば、相続人間の不要な対立を回避できます。
「自分が亡くなった後の話をするなんて縁起でもない」と思われがちですが、実際はとても大切な家族の話です。
きっかけがあれば、意外とスムーズに話せるもの。たとえば帰省のタイミングや、年末年始、誕生日などを利用してみてください。

「うちは家族仲がいいから大丈夫」
「財産なんて大した額じゃないし、揉めるはずがない」
そう思っているご家庭ほど、話し合いや準備を後回しにしてしまい、いざ相続が起きたときに混乱を招くケースが多いのが実情です。
相続は、お金の話であると同時に、人間関係の話でもあります。
少しでも気になった方は、今のうちに「財産の見える化」「遺言の検討」「家族との対話」など、できることから始めてみてはいかがでしょうか。
ご不明な点や不安な点がある方は、税理士などの専門家にご相談ください。あなたのご家庭が“揉めない相続”を実現できるよう、お手伝いさせていただきます。
